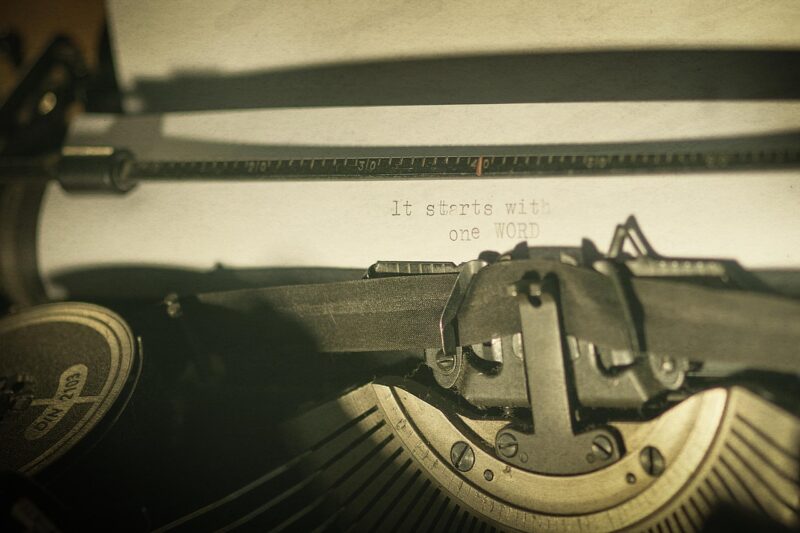タグ付けするということ

前々回に、「言葉は額縁になる」という話をしました。最近それと同時に額縁=タグ付けする・されるということの怖さみたいなものを感じる時があります。
どこかの誰かが「子供の頃親がよく車で聞いていた曲は、曲名を知った瞬間に別の曲になってしまう」ということを書いていました。
人間誰しも「わからないもの」を恐れて、捨てるor「わかるもの」にしようとする傾向があると思います。「いじめ」や「村八分」の風習がわかりやすい例だと思います。
自分も大人になるにつれてその癖が抜けなくなってきました。
最近の世の中も全てのものにタグ付けされる傾向が強くなってきました。
世代、ジャンル、カテゴリ、MBTI、さらにはその個人の好みにまで合わせて最適かされます。この機能自体はとても便利なもので間違いはないと思います。日常生活に限らず、マネジメントやマーケティングにおいても効率上昇には欠かせない機能でしょう。
これが怖いと感じるのは、この極度に細分化され合理化されたもののみを受け取っている自分たちの視野は、もしかしたら極端に狭まっているのではないかということです。
これはおそらく大人になればなるほど悪化して行くのでしょう。
なぜなら「わかった」ものが増えて行くからです。そしてわかったものたちで周りを埋めていきます。さらにそこに新しく入ってきたものは捨てるorすでに「わかったもの」とタグ付されたものにチューニングし嵌め込もうとします。わからないものをわからないままおいておくのが怖いからです。こうして「わかったもの」のみで形成された世界ができます。
「郷に入っては郷に従え」という言葉がありますが、これはどこまでが有効なのでしょうか。規則?習慣?好み?正解はバラバラかもしれません。
今の世間の世代間ギャップが大きいのはこの価値観のグラデーションの差異が大きいと思います。
例えば上の世代が好みまで合わせましょうというのに対して、下の世代は規則のみ共有していればよくないかというような違いです。
わかりやすくいうと、上の世代がタグ付けしたもの7:わからないもの3で生きているのに対して、若い世代がタグ付けしたいもの3:わからないもの7で生きたいというような価値観の違いから生まれるギャップなのだと思います。
これはもっと前の年代からあったものだとは思いますが、SNSや「多様性」という言葉の普及によって顕著に問題となって現れている気がします。
会社のような組織(上の世代)としては、統率を取るためにタグ付けをしたい。個人(下の世代)としては、共有事項が増えて何か(組織に貼られているタグ)に縛られたりせず自由に暮らしたい。おそらくどっちも正解で不正解なのでしょう。
ただ下の世代も意識しなきゃいけないのは、今受け取っているタグ付けによって合理化・最適化された情報は上の世代が作ったものであるということです。全部とは言いませんが、視野が狭まっている人が作ったものを視野が狭まった人たちが受け取っているという構図が起きていてもおかしくありません。
ただこのタグ付けの習慣はAIによってさらに加速して行くと思います。
そうすればタグ付けされた「わかるもの」が増えていきます。
それに慣れてしまっていくのが怖いと思う根幹の要因かもしれません。
自分自身も大人になって行くにつれて「わかったもの」が増えて行くと思います。そうしたときに今と逆の世代間ギャップを感じることもあるでしょう。
そのときに「どちらも正解で不正解」という意識は持ち続けていきたいなと思います。
今回は少し重めな話になったので、次は旅行で行きたいとこでも並べようかなと思います。それではまた。